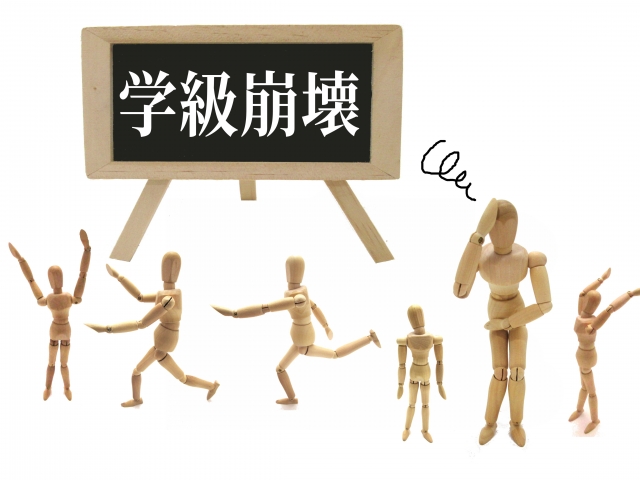不良がリーダーになるのを止められない担任

1.体育祭のカラーリーダー廃止の提案
A中学校に赴任した年の9月。
職員会議で3年部の教員から次のような要望がありました。
「カラーリーダーの制度を廃止しませんか?」
「ヤンチャ(不良)の子供達がカラーリーダーをやりたがって困るんです。」
「下級生にも悪い影響を及ぼしますし・・・・。」
「カラーリーダーを廃止し、学級委員を体育祭のリーダーとしてはどうでしょう?」
A中学校では体育祭を行う前に、3年生から「カラーリーダー」を選ぶという伝統がありました。
カラーリーダーとは各カラーの代表となり、「カラー種目」の「練習計画」を考え、指示を出したり、準備をしたりするのが仕事です。
当然ですが、カラーリーダーになれるのは3年生で男女1人ずつです。
「青組!」
「気合いれろー!」
「絶対に優勝するぞー!」
『オー!』
このような檄を飛ばすのもカラーリーダーの仕事です。
そのため、元気のある子(ヤンチャな子)がカラーリーダーをやりたがる傾向にありました。
2.目立ちたいだけで計画性のないリーダー達
職員会議の話を聞いていると、この学校の「カラーリーダー」がどのようなものか分かってきました。
・ヤンチャな子供(不良系の子供)がカラーリーダーをやりたがる。
・その子供たちは「練習計画」を立てることができない。
・事前に準備をしたり、考えたりせず、その場の思いつきで行動する。
・計画や進行が悪いにも関わらず指示だけは「エラそう」に出す。
・校則違反の服装(シャツだし、腰パン)で練習を行う。
・同じカラーの下級生が、校則違反の服装を真似する。など
3年部の教員が「カラーリーダー廃止」の提案をすると、他の先生たちが口々に意見を言い出します。
「去年の赤組のリーダーはひどかったよね!」
「計画は立てないし、準備はしないし!」
「練習が始まってから練習内容を決めるんだよね!」など
すると、去年の3年担任が次のように言いました。
「自分で立候補したんですよ!」
「そのクセ、面倒な事はやらないんです!」
「後輩が自分の思い通りに動かないと怒るんですよね~。」
「エラそうに指示ダケは出すんですよね~。」
「あの子は本当に口ばっかりでした!」
3.子供の問題ではなく担任の決意の問題!
聞こえてくる声に「イラッ」とした私は、次のような発言をしてしまいました。
「システムの問題じゃないと思います!」
「担任がどれだけ支援するかの問題ではないですか?」
これに対して司会の先生は次のように質問をしてきます。
「それは、どういう意味ですか?」
「詳しく説明をして下さい。」
私は思ったことを正直に言ってしまいます。
「私の前任校にもカラーリーダーはありました。」
「この学校と同様で『ヤンチャな子供達』が立候補します。」
「ただ、私はその子供たちがリーダをする事に反対はしません。」
「やる気を持つことが大切だと思っているからです。」
そして、次のようにも言ってしまいます。
「私は『ヤンチャな子供達』にリーダーとしての心構えを伝えました。」
「そして、事前の計画や準備は必須であると言います。」
「シッカリと覚悟を持たせてからリーダーをやらせたのです。」
「もちろん、事前に計画や準備の相談を受けたり、確認をしたりしました。」
「要は教師の覚悟や支援の問題だと思うのですが?」
『自分から立候補したのだから、良いリーダーとなれるように支援をしよう!』
『立派なカラーリーダとなれるようにフォローしよう!』など
4.不良の子供たちの言いなりになってしまう教員
私の意見を聞いた先生達はヒソヒソ話を始めます。
「そうは言ってもね~。」
「立候補制にすると真面目な子供が立候補できないしね~。」
「不良の子供は自分勝手で言うこと聞かないし~。」
私に聞こえるか聞こえないかの声で、次のように言う先生もいました。
「西川先生が前にいた学校は落ち着いていたんでしょうね~。」
「この学校の子供たちのレベルを分かってないんだよ!」
「3年生がどれだけ悪いか知らないんだ!」
「子供たちの状態を知らないくせにエラそうに言わないでほしいよね~。」など
私は前任校の「荒れ」を改善させた人間の1人です。
また、「荒れている学校」に異動させられ、「生徒指導主事」と「3年担任」をさせられたこともあります。
多くの「荒れ」を経験している私にしてみると、A中学校の3年生は「カワイイ」部類ではあるのですが・・・。
5.学年の男女ボスがカラーリーダーに立候補!
赴任してスグの先生が「荒れている学年」の「担任」や「教科担任」となるのは、「学級崩壊あるある(荒れた学校あるある)」の1つです。
実際、私も赴任してスグの学校で「最も荒れている3年生の担任」をしたことがあります。
さらに言うと、私が「生徒指導主事」として赴任することが分かっていた学年主任(?)は、「男子学年ボス」と「女子学年ボス」の2人を私のクラスにしていました。
当然ですが、その2人は体育祭のカラーリーダーに立候補して選ばれます。
ただ、私はカラーリーダーに決まった2人に対し次のような話をしました。
「やるからには、下級生の見本となるリーダーになってもらう!」
「後輩がお前たち2人を目標にする位のリーダーになりなさい!」
「もちろん、そのために服装もしっかりとしてもらう!」
「練習計画も事前に立ててもらう。(最初はチェックしていました)」
「そして、当日は全体の前で堂々と指示を出してもらう!」
当然ですが、次のようにも伝えます。
「やる気のない態度を見せたら1~2年生の前でも怒鳴る!」
「服装が乱れていたときも同様だ!」
「それがイヤなら、カラーリーダーを辞退してくれ!」」
「もちろん、本気でやる気持ちがあるなら、先生も全力で協力する!」
「コピーや印刷、必要な物の準備などの雑用もする!」
6.カリスマ性が良い方向に向くように!
この2人は、前年にそれぞれのクラスを「学級崩壊」に導いたボスでした。
ただ、良くも悪くも「カリスマ性」や「リーダーシップ」「負けず嫌いの気持ち」を持っています。
そんな彼らは、私の言葉をきっかけに「カラーリーダー」に本気で向き合うようになりました。
2人で事前に練習計画を立て、私に確認や相談を繰り返します。
お互いの役割分担も決めて、それに従って仲間や下級生に指示を出していました。
これにより、この2人は「良い意味」で下級生から尊敬される存在になったのです。
7.成功体験により学業の集中力が高まる!
体育祭で「カラーリーダー」の役割を見事に務めた2人は、自分に自信を持つようになります。
その自信は他の学校生活にも表れてきます。
放課後に練習計画を一緒に考えたことがキッカケとなり、2人は「放課後勉強会」をするようになりました。
そんな2人は勉強会で分からない問題があると、スグに私の所に聞きに来るようになっていました。
これにより、それまでは普通に授業を受けていたダケの2人でしたが、挙手や発表を積極的に行えるようになったのです。
※ 1~2年の時は授業中に寝たり、出歩いたり、別の事をしたりしていたそうですが、3年生の4月からは普通に授業を受けるようになりました。
その結果、男子学級崩壊ボスは「内申点」が6つも上がり(元々がオール2でしたが)、女子学級崩壊ボスは「内申点」が4つも上がったのです。
8.カラーリーダー廃止に3年生が怒ると
職員会議では「3年部の意向を尊重する」ということで、「カラーリーダー」の制度は廃止となりました。
しかし、廃止を知った3年生からは、次のような声がたくさん上がったようです。
「何で今年はカラーリーダーがないの?」
「カラーリーダーをやるつもりだったのに!」
「おかしくない?」
「ふざけるな!」など
ただ、これに対して3年部の先生は、次のように説明をします。
「職員会議で決まった事だから仕方ないよ。」
「本当はカラーリーダーの制度は残したかったんだけどね~。」
「先生達が話し合って決めた事だからね~。」
「決まったことを変えることは出来ないんだよ~。」
3年部か「廃止案」を提出して、それが認められた形なのですが・・・。
反対したのは、私と数人の先生だけだったのですが・・・。
9.カラーリーダーになるために○○になった不良少年
その後はどうなったのでしょう?
翌年の3年生には「カラーリーダー」をやりたいがために、前期学級委員になった「ヤンチャな子供」がいました。
担任の先生達は、まさか「ヤンチャな子供」が学級委員に立候補するとは思っていなかったようです。
そして、学級委員になった「ヤンチャな子供達」は学級委員の仕事を中途半端に行います。
これに困ったのは新3年部の先生達です。
その結果、翌年の職員会議では3年部の先生から、次のような提案が出されます。
「カラーリーダーを学級委員が兼務するのは良くないと思います。」
「そこで、今年はカラーリーダー制を復活させたいと思います。」
「次のようにしてもいいでしょうか?」
『多くの子供にリーダーの経験をさせたい。』
『そのため、学級委員はカラーリーダーになることはできない。』
『ただし、委員長や生徒会の生徒は除くものとする。